格言の宝庫、セネカの言葉を紹介する。
セネカの著書『幸福な人生について』から今回は抜粋する。
紀元前に生きた彼の言葉は、現代を生きるわたしたちの心にも響くものが多くある。

最高の幸福とは、場当たり的に行動することを恥とし、高潔を尊ぶ心を持つことである。
最高の幸福とは、経験による知恵を持ち、行いが物静かで、他人との交わりではいつも礼儀正しく、しかも気配りを怠らず、毅然とした心を持つことである。
この二つのことは、同義であるとセネカは言う。
現代の言葉で短くまとめるとするならば、「自分で考えて自分で生きろ」ということだろう。
言葉でいうには簡単だが、これを実践するとなるといきなり難しくなる。
日本人は義務教育の段階から自分で一人で生きていく感覚から遠ざけられている。常にだれかと共に生きていく、困ったら誰かが助けてくれる。なぜかそんなような雰囲気に包まれている。
慶応義塾大学を創設した福沢諭吉は人間に必要なのは「自立」にあると説き、慶応の校訓にした。
こういう考え方を幼いころから身に着けておくと、幸福な人生を送りやすい。すでに歳を重ねてきた人も、いまからこの考え方を肝に銘じれば、幸福な人生になるかもしれない。
幸福な人とは、名誉を大切にし徳を行うことを喜びとし、その場かぎりのことで得意がったりくじけたりしないで、自ら選んで自らのために行う善を最高とし、快楽を恥とする人、と定義することができる。
今どきこんな人がいたら周りから聖人と揶揄されるだろう。
しかし、こういう「人のためにすることが幸福だ」論では珍しく、セネカは自分のために行う善こそが最高だと言っている。
しかし、そのすぐ後で欲はダメだとも言っている。要は、勉強・スポーツ・芸術などは善であり、酒・女遊び・贅沢などは欲として分けろと言っている。
自分のための善になることにいくらでも時間を使っていいとセネカはいう。そもそも、自分のためにならない仕事は時間の無駄だと言い切っている。
自律性という視点からみれば、幸福な人とは、理性の資質によって恐怖心や欲望から解放されている人であるともいえる。
岩石は恐怖や悲しみから解放されているし、野原にすむ動物たちも同じかもしれない。しかし、岩石や動物たちには幸福という認識がないから、彼らは幸福であると言うことはできない。したがって、生まれつき愚かなために、あるいは自分をわきまえないために、野の動物たちや生命を持たない物と同じレベルに落ち込んでいる人々は幸福を味わうことはできない。
たとえ分別があっても、心がゆがんでいれば悪い方向に働くから、もの同然になり下がった人間と変わりはない。真理がわからなくなった人間に幸福感は与えられない。
以上4つがセネカのいう「幸福の定義」である。
最後の項の説明を以下に載せる。
幸福な人生とは、正しくて信頼に値する思慮分別の上に打ち立てられる不変のものをいうのである。心に曇りがなく、深い傷はもちろんかすり傷さえ心に負わせず、どんな悪にも心を染ませまいと決意し、また、どんな道を進むにせよ、目標をあくまで堅持しようという覚悟が決まっていれば怒りの神も避けて通るに違いない。
ところが、人の心の中には悦楽を求める気持ちがひそんでいるのである。心のおもむくままに任せてみるがよい。感覚を喜ばせるものを飽食し、消えようとする過去の悦楽を振り返って酔いしれ、次にくる快楽を待ち望む。善を求めず悪を選ぶ結果、心はすさんで、浅ましいものに成り下がっていくだろう。
分別に富んでいなければ幸福にはなれない。幸福な人は正しい判断力をもっている。たとえそれがどんなものであろうとも現在のめぐり合わせに満足し、自分の境遇に黙って従い、自分が置かれている状況を理性的に判断できる人こそ幸福なのである。
最後の項こそが、幸せとはなんなのかを教えてくれている。と、私は感じる。
現在のめぐりあわせに満足すれば、高望みをして絶望することはなくなる。
幸福とはとらえ方で形は簡単に変わるものだ。

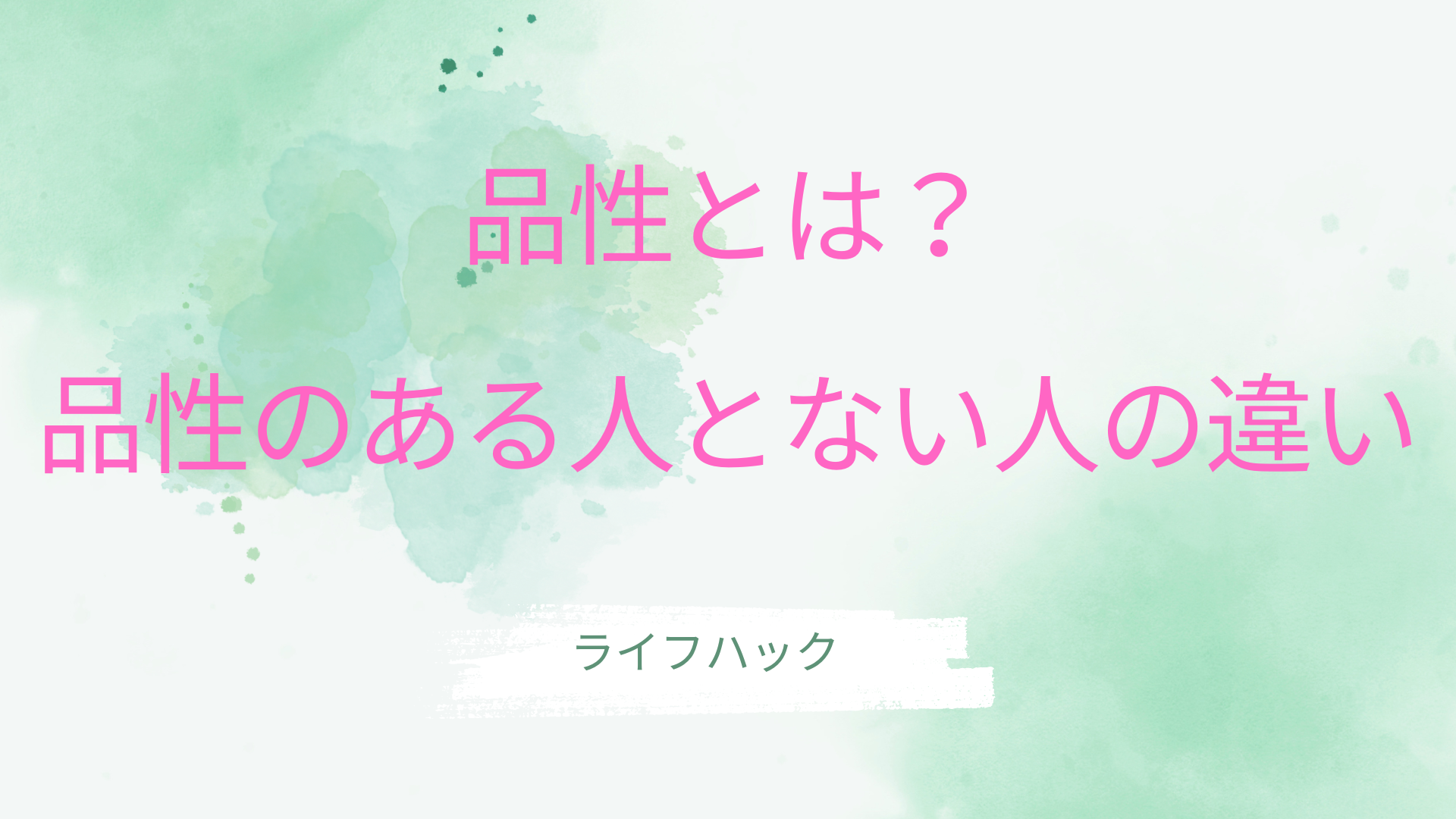
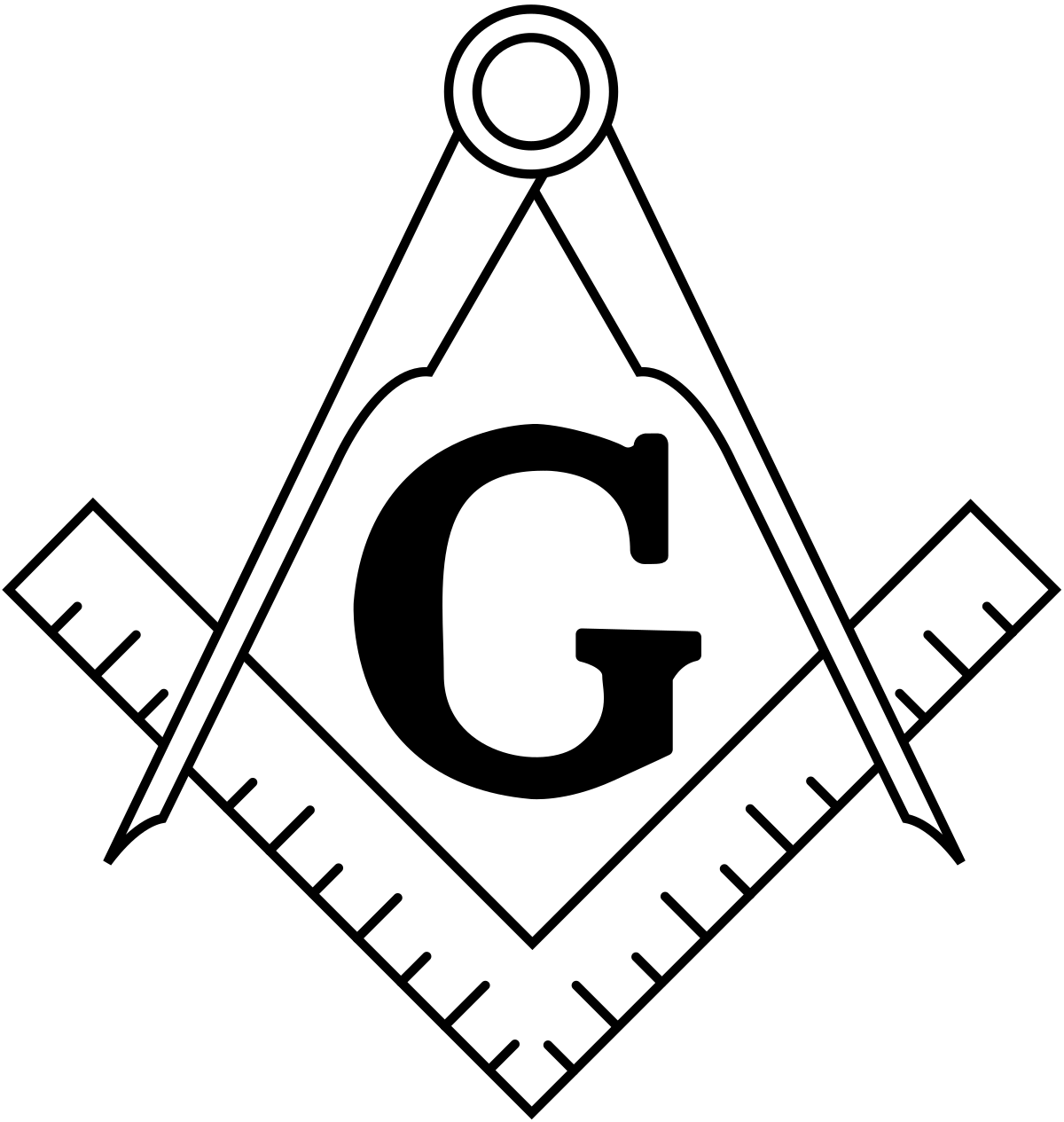

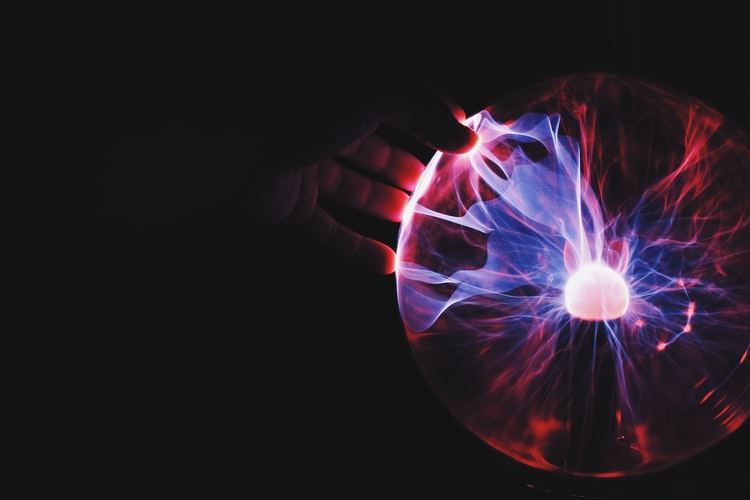

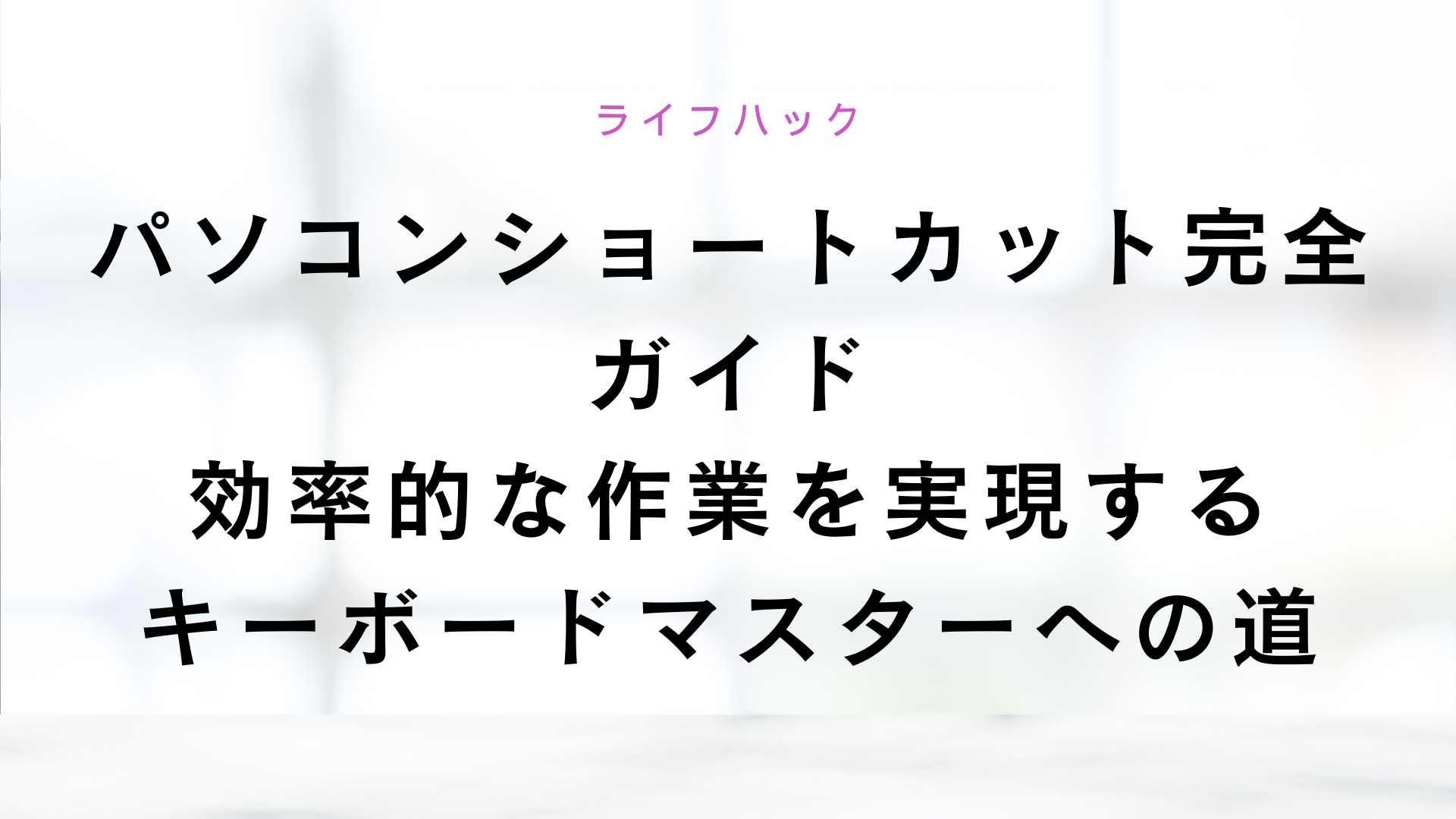






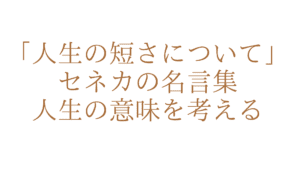





コメント